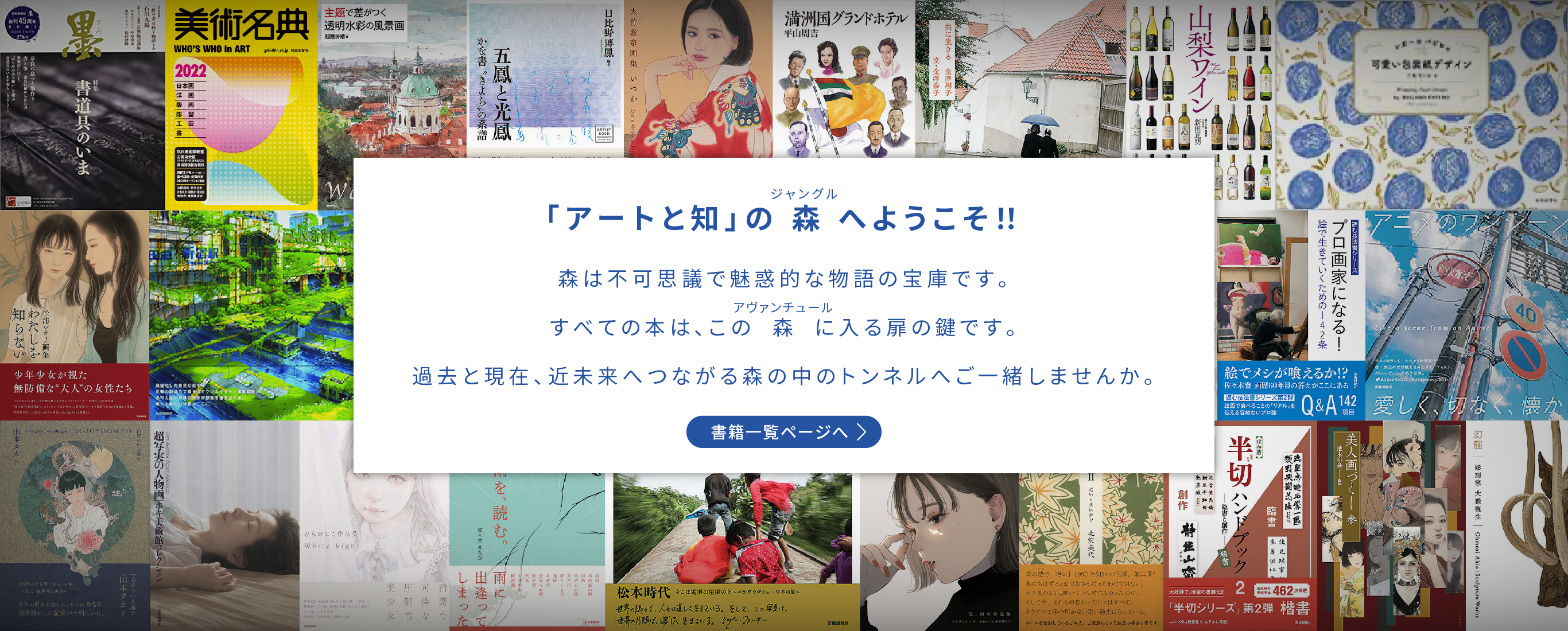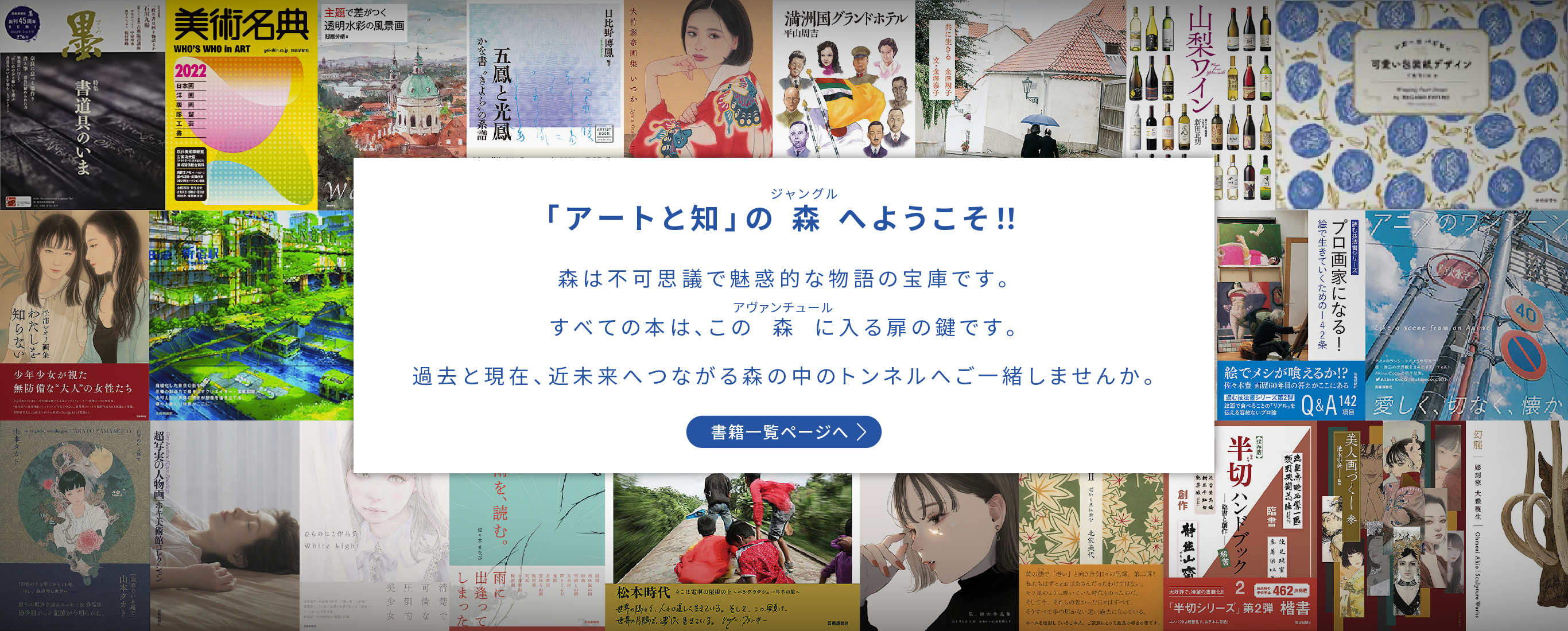-

墨2026年1・2月号 298号
¥2,970
【特集】表具うつくし 書き終えた作品の魅力をより一層引き出してくれる表具。 古くから書と深く関わってきた表具の世界には、 長い歳月のなかで磨かれてきた美と技が、今も脈々と息づいています。 本特集では、表具の基礎知識をはじめ、修復の現場、表装の現場、 書家と職人それぞれの視点を通じて現代の表具事情を探ります。 基礎知識 そもそも表具とは何か? レポート 修復の現場 協力/彫美堂G.K. インタビュー 文化財修復のいま 談/金子馨 レポート 表装の現場 あなたの作品が完成するまで 協力/盛洋堂株式会社 対談 書を輝かせる表装の疑問に迫る 齊藤紫香×湯山大督 スポット 表具師と書家の思い ―第8回表装展を振り返る― 協力/東洋額装株式会社 赤澤寧生 阿部泰秀 有信柏翠 奥村 章 河﨑鵬堂 川本大幽 金城翔山 阪野 鑑 桟敷東煌 西田 健 山﨑慎也 山本山罍 吉澤太雅 コラム 自宅で裏打ちに挑む 講師/表導会 【企画】 ・第118回 日展 代表作家作品 主要賞 文部科学大臣賞/東京都知事賞/日展会員賞 特選 会場だより 第5科入選者一覧 ・書道界マップ 2025年 主要団体受賞者 2026年 新年名刺交換会 近現代書の人脈 近現代書 団体の成立と変遷 【連載】 ・館蔵の名品⑪ 嵯峨嵐山文華館 伝長谷川宗圜「百人一首手鑑」 解説/國永裕子 ・創作のための古典臨書講座 漢字④ 遅速緩急(王鐸・傅山) 容易語・草書杜甫詩軸 指導/山本大悦 ・創作のための古典臨書講座 かな④ 散らし書き 関戸本古今集 (4行の散らし書き)(文字群の配置を変える) 指導/近藤浩乎 ・羽ばたけ!書の未来へ① 文/松村香露 ・デザイン書道講座④ 文/久木田ヒロノブ ・墨アーカイヴ 宮本竹逕 ・時代と人と書 かな篇① 日本の特質と古代の王朝 文/井口尚樹 【トピックス】 インフォメーション ・九州女子大学主催 第37回高等学校揮毫大会 ・大東文化書道研究所の「書への眼差し」DVD+一般のための通信書道講座 ・令和7(2025)年度 大学卒業制作展 掲載校大募集 レポート ・刻之共鳴 竹市求仙・何柏青 日中刻字芸術交流展 特別寄稿 ・書の旅 続・河南省編(中)嵩山三闕を訪ねて 文/髙澤浩一 ・辛亥革命中の張裕釗書法 文/魚住和晃 読者参加企画 ・297号作品募集結果発表 審査/久木田ヒロノブ・山本大悦・近藤浩乎 【展覧会】 [プレビュー] ・第36回幕田魁心の書 [話題の展覧会] ・平安王朝美の再現者 ――田中親美と尾上柴舟――展 ・初見 石川九楊展 ・古新典麗 東京国際甲骨文書道展 ・茅原南龍 書業六十五年ふるさと展 筆魂の響き ・第56回 玄武書道展 ・第60回 現創会書展 ・伊山宗紫書作展――こ・こ・ろ―― ・第47回 東京書作展 ・吉田鷹村遺作展 ・特別展 良寛の書簡 ・第43回 古典臨書展 [話題の書道展より] ・第47回 日本書展 第52回 銀河書道作品展 ・第74回 奎星展 ・第13回 日本書道院「100人」展 【墨らんだむ】 ・書道通信 ・新刊ぴっくあっぷ ・読者の広場 ・展覧会ルポ ・展覧会セレクション ・展覧会アラカルト ・1・2月の展覧会スケジュール ・バックナンバー一覧 ・愛読者プレゼント ・編集部日記 ・常設書店リスト ・次号予告/編集後記
-

墨2025年11・12月号 297号
¥2,970
【特集】篆書の表現 最古の漢字書体である篆書。 篆書作品ならではの注意事項は? 時代や地域により異なる文字どうしの書風の揃え方は? 字形の調整はどこまで許されるのか? 学習者の素朴な疑問に寄り添いながら篆書の歴史、 学び方、表現に役立つ具体的なテクニックから 現代作家の作品までご紹介。 皆様を篆書の世界へ誘います。 ともに一歩進んだ篆書の表現を目指しましょう。 導入 書作に役立つ 篆書の基礎知識 文/中村信宏 コラム 金文の鋳造技法 解説/山本堯 知識 『総合篆書大字典』編者・綿引滔天氏に聞く 異なる書風の揃え方 談/綿引滔天 視点 公募展における篆書作品の傾向 談/牛窪梧十 実践 金文と肉筆から 篆書の表現を考える 講師/池田毓仁 鑑賞 わたしの篆書表現 秋山浩志 川内伯豐 松尾碩甫 宮迫嗣君 【恒例企画】午年生まれの書家の年賀状 【連載】 ・館蔵の名品⑩ 澄懐堂美術館 孫星衍 臨碧落碑 十六屛 解説/井後尚久 ・創作のための古典臨書講座 かな③ 行の響き合い 関戸本古今集 (行間を広く取ってみる)(行間を狭くしてみる) 指導/近藤浩乎 ・創作のための古典臨書講座 漢字③ 文字の懐(顔真卿) 祭姪文稿・争座位稿 指導/山本大悦 ・デザイン書道講座③ 文/久木田ヒロノブ ・最終回 天真を養う㉚ 文/玄侑宗久 ・墨アーカイヴ 小坂奇石 ・時代と人と書 篆書篇③ 刻石の真の筆者は? 文/井口尚樹 【トピックス】 フォーカス ・生誕百二十年記念 三村秀竹の世界 レポート ・鎌田悠紀子ブラジル紀行 インタビュー ・中国語版『中國書史』、新刊『書を学ぶあなたへ』出版記念 石川九楊特別インタビュー 特別寄稿 ・書の旅 続・河南省編(上)尹宙碑を訪ねて 文/髙澤浩一 ・「草隷」の実相 ――睡虎地・里耶簡牘を中心として―― 文/横田恭三 ・會津八一と『ほとゝぎす』 文/小川貴史 読者参加企画 ・296号作品募集結果発表 審査/久木田ヒロノブ・山本大悦・近藤浩乎 【展覧会】 [プレビュー] ・第25回扶桑印社展 併催 毎日書道顕彰受賞記念「扶桑印社展の25年」 ・竹市求仙・何柏青刻字芸術展――寿山福海―― [話題の展覧会] ・生誕百二十年記念展 三村秀竹 ・第65回記念 璞社書展 継承―回顧から更なる発展へ― 特別展示 璞社会長の足跡―小坂奇石 江口大象 山本大悦― ・第42回産経国際書展 ・西泠印社日本名誉社員作品展 ――呉昌碩胸像寄贈45周年記念―― ・第41回読売書法展 ・傳承有道・大書法國際名家(東京)邀請展 張華慶大書法藝術館乙巳特展 ・生誕百年記念 小林抱牛展 〜魂はハジケ出る!今ふたたび〜 ・圡川碧雲書展 [話題の書道展より] ・第68回 凌雲書展 ・第64回 現日書展 ・第64回 白扇書道会展 【墨らんだむ】 ・書道通信 ・新刊ぴっくあっぷ ・読者の広場 ・展覧会ルポ ・展覧会セレクション ・展覧会アラカルト ・11・12月の展覧会スケジュール ・バックナンバー一覧 ・愛読者プレゼント ・編集部日記 ・常設書店リスト ・次号予告/編集後記
-

墨2025年9・10月号 296号
¥2,970
採拓から鑑賞まで 拓本を見よ! 書を学ぶ人のパートナー「拓本」。今号は採拓から鑑賞方法まで紹介し、その味わい方を提案します。ただ書の手本として見るだけでは勿体ない! 拓本の裏側には様々なドラマが存在します。筆技を読み取るだけではなく、採拓の方法や周辺情報も学ぶことで読解力は格段に上がるはず。ステップアップを目指すあなたの強い味方です。 基礎知識1 拓本の基礎知識 文/編集部 実践1 拓本の採り方 鑑賞1 行成かなの拓本を味わう コラム 蘇った『尚古法帖第十八 行成卿』 文/横倉佳男 実践2 かな拓本の楽しみ 橋本貴朗 基礎知識2 碑法帖拓本の見方 文/伊藤滋(木雞室) 鑑賞2 木雞室選 漢碑の拓本を味わう 選・文/伊藤滋(木雞室) 視点 鄭道昭と四嶽摩崖刻石 文・写真/坂田玄翔 PARIS パリ INALCO 顚末記 文/坂田玄翔 レポート 木俣曲水顕彰碑の採拓 拓本を採りに行こう 文/編集部 学習 拓本制作から臨書まで 線書きの意味 解説/日野楠雄 鑑賞3 書壇院所蔵の名拓 談/柳澤朱篁 【企画】 万博レポート 白と黒の伝統――書と囲碁の世界―― The Legend of Black & White 墨いろの軌跡――産経国際書展 大阪・関西万博展―― The World “SHO” ――Japanese calligraphy―― 【連載】 ・館蔵の名品⑨ 多胡碑記念館 広開土王碑拓本 解説/岡村友理香 ・創作のための古典臨書講座 漢字② 抑揚と線の太細(米芾) 張季明帖・苕渓詩巻 指導/山本大悦 ・禾陸の会 上海書法通信④ 八者八様の筆致 from 第 25回記念 蘭亭書法交流【寧波展】 ・創作のための古典臨書講座 かな② 動きの表現(右上がりの展開)(右下がりの展開) 関戸本古今集 指導/近藤浩乎 ・天真を養う㉙ 文/玄侑宗久 ・デザイン書道講座② 文/久木田ヒロノブ ・時評 揮灑㉟ 文/亀井一政 ・墨アーカイヴ 青山杉雨 ・時代と人と書 篆書篇② 始皇帝の建てた七刻石 文/井口尚樹 【トピックス】 レポート ・第25回記念 蘭亭書法交流 寧波展 読者参加企画 ・295号作品募集結果発表 審査/久木田ヒロノブ・山本大悦・近藤浩乎 【展覧会】 [プレビュー] ・観峰館 開館30周年特別企画展 王羲之からの手紙 ――国宝「孔侍中帖」と中国書法名品選―― ・第13回 聖心書展 [話題の展覧会] ・加藤子華 書の世界 ――書の美を求めて―― ・第53回 日本の書展 ・第76回 毎日書道展 ・第12回 一瀾書道会 結成15周年記念展 ・第43回 日本詩文書作家協会書展 ―第35回 伊藤園お〜いお茶新俳句大賞入賞作品を書く― ・武内枝雪 百寿記念書展 ―生ある歓びⅡ― ・米寿記念 書と教育 二刀流展 笠原秋水 個展 こころを言葉に ことばを書に ・佐藤浩苑書展 [話題の書道展より] ・第38回 書道 玄燿展 ・2025 独立選抜書展 ・第86回 国際文化交流 大日本書芸院展 ・第48回 由源展 ・第63回 墨滴会全国書展 ・第39回 玄心書道展 ・第23回 滴仙会書法展 ・第62回 水穂書展 ・第74回 玉信書展 ・第53回 國際書道連盟展 【墨らんだむ】 ・書道通信 ・新刊ぴっくあっぷ ・読者の広場 ・展覧会ルポ ・展覧会セレクション ・展覧会アラカルト ・9・10月の展覧会スケジュール ・バックナンバー一覧 ・愛読者プレゼント ・編集部日記 ・常設書店リスト ・次号予告/編集後記
-

墨2025年7・8月号 295号
¥2,970
【雑誌】 判型:A4変型 並製 頁数:216頁 【特集】 飯島春敬のしごと 春敬記念書道文庫の名筆 かな書家、古筆研究者、古筆蒐集家として名を馳せた飯島春敬(明治三十九~平成八年)。春敬は、古典書道の学問的研究を目的として、 昭和二十二年に書道文化院(現在の一般社団法人書芸文化院)を発足させました。さらに同五十八年には、同院内に「春敬記念書道文庫」を創設し、自ら蒐集した名筆の数々を収蔵しています。また、同院は昭和二十五年より「平安書道研究会」を主宰。 これは毎月一回、名筆を出陳しながら講義を行う研究会で、今年ついに記念すべき第九〇〇回を迎えました。 この節目を記念し、六月から春敬の蒐集品が五島美術館の館蔵品とともに同館で展観されています。 今号は春敬の足跡を辿り、書にかけた情熱やその審美眼に焦点を当てます。 春敬記念書道文庫の名筆も豊富にご紹介。春敬の「しごと」を改めて振り返りましょう。 歴史 ★飯島春敬が遺したもの 監修/飯島太比呂 ★飯島春敬の書 選/飯島太比呂 鑑賞 ★春敬記念書道文庫の名筆 選・解説/飯島太比呂 解説/伊藤 滋 レポート 潜入!平安書道研究会 レッスン ★原寸臨書から拡大臨書まで 古筆に臨む 講師/松井玉箏 アーカイヴ 書評論家・田宮文平がみた飯島春敬 エッセイ 飯島春敬の審美眼 蒐集への情熱 文/名児耶 明 インフォメーション 展覧会「極上の仮名 王朝貴族の教養と美意識」 【企画】 万博レポート ◆未来へつなぐ日本の書〜空・海・時を超えて〜 ◆大阪・関西万博で「日中書道交流会」開催
-

墨2025年5・6月号 294号
¥2,970
【雑誌】 判型:A4変型 並製 頁数:224頁 【特集】 俳句を書く 省略を極め、わずか十七音で豊かな世界を表現する俳句。 美しいことばや言い回し、素材から受けた感動を書に表現しませんか。 日本特有の美意識や自然観が凝縮された〝俳句〟の書表現を考えます。 先人たちが選んだ名句と作品、歴代俳人の書も鑑賞。 実践レッスンでは、作品展開の具体的ポイントや 表現のテクニックなどに迫ります。 墨場必携としての名句選も紹介。 機知を味わい、ユーモアを楽しむ俳句の書表現を楽しみましょう。 【企画】 令和6年・2024年度 大学卒業制作展
-

墨2025年3・4月号 293号
¥2,970
【雑誌】 判型:A4変型 並製 頁数:264頁 【特集】漢字条幅を学ぼう 漢字書の作品形式のひとつ「条幅」。 清々しい紙面に、自由に、そして表情豊かに 作品を展開させたいものです。 今号は漢字条幅の表現について、いま一度学びます。 先人たちの作品のほか、活躍中の現代作家による 書き下ろし作品を通して、表現のポイントや見せ場、 紙面構成など漢字条幅作品のまとめ方を紹介。 『墨』電子版の刊行を記念する特別号として増頁でお届けします。 表現の無限の可能性を探り、引き出しを増やしましょう。 視点 学芸員の視点でみる半切という紙面 解説/鈴川宏美 レッスン 最後まで気を抜かない 漢字作品の落款 講師/西 墨濤 鑑賞 現代書家 漢字作品選 新井龍雲 生駒蘭嵩 石川青邱 今口鷺外 内山玉延 尾﨑司邑 尾西正成 小出聖州 小林逸光 小林翠径 阪野 鑑 鈴木曉昇 関口鶴情 髙見廣流 種家杉晃 種谷萬城 長澤幽篁 中村草殷 二宮奇龍 丹羽蒼處 日賀野琢 疋田惜陰 廣畑筑州 平樂大龕 松川昌弘 松村博峰 茂住菁邨 コラム 書の造形と配置をデザイン視点で考える 文/久木田ヒロノブ 【恒例企画】2025新春展 ・第69回 現代書道二十人展 ・現代の書 新春展——今いきづく墨の華—— セイコーハウス展/セントラル会場100人展 ・第41回 産経国際書展 新春展 第39回 産経国際書展代表展
-

墨2025年1・2月号 292号
¥2,700
【雑誌】 判型:A4変型 並製 頁数:216頁 【特集】昭和100年記念 時代の書 1926年に改元され、日本史上最長の元号となった昭和。 2025年は昭和100年に当たります。 今号は激動の時代、昭和を振り返るとともに 昭和書道史を概観します。 昭和の書壇で活躍した作家の名品を 主要な展覧会の歴史・書道団体成立の系図など、 便利な資料とともにお届けします。 書を通じて、昭和という時代を回顧してみましょう。 インタビュー 昭和の書文化と書壇を語る 談/西嶋慎一 視点 私の見た書の昭和 「読む」から「見る」へ 書が美術へ接近した時代 談/菅原教夫 激動と秩序の共存していた昭和は身近にいつも書があった 文/比田井和子 周囲一メートルの昭和 文/桐山正寿 衝突と賛否両論が多様性を育んだ 談/松原清 鑑賞 昭和を生きた書人、書と言葉 選/井口尚樹 比田井天来 川谷尚亭 中村不折 吉田苞竹 会津八一 鈴木翠軒 高村光太郎 比田井南谷 川村驥山 津金寉仙 上田桑鳩 大澤雅休 井上有一 尾上柴舟 西川寧 辻本史邑 豊道春海 上條信山 松本芳翠 安東聖空 深山龍洞 赤羽雲庭 手島右卿 木村知石 青木香流 日比野五鳳 松井如流 森田竹華 金子鷗亭 森田子龍 村上三島 西谷卯木 殿村藍田 小坂奇石 柳田泰雲 宇野雪村 桑田笹舟 今井凌雪 青山杉雨 河井荃廬 石井雙石 中村蘭台二世 山田正平 コラム 昭和の書家のしごと 固形墨の題字 コラム 昭和の書家のしごと 筆墨店の看板文字 資料室 近現代書の人脈 資料室 近現代書 団体の成立と変遷 資料室 墨展覧会リバイバル 第36回毎日書道展/第1回読売書法展/ 第1回サンケイ国際書展 【企画】第11回 日展 第5科・書
-

墨2024年11・12月号 291号
¥2,700
【雑誌】 判型:A4変型 並製 頁数:192頁 【特集】日常の楷行書を考える 書を学ぶ者であれば、日常の文字は美しく書きたいもの。 毛筆の鍛錬は欠かさないけれども、 ちょっとしたメモ書きで硬筆を執った際にうまく書けない。 そんな経験はありませんか? 今号は年賀状シーズンに合わせて 日常の文章を美しく書くコツをご紹介します。 小さな楷行書の世界から、硬筆、毛筆を含めて 美しい文字を目指しましょう。 基礎知識 〝読みやすさ〟と〝書きやすさ〟の原点 漢字の発生と楷書・行書の誕生 解説/中村信宏 鑑賞 書くための目習い 小さな楷書・行書の名品選 選/中村信宏 レッスン 実践 毛筆小字楷書・行書入門 小字の美を見直そう 講師/赤平泰処 レッスン 実践 硬筆書道 美しい書き文字 講師/鈴木啓水 資料室 ふだん使いの筆ペンと万年筆を深掘る 呉竹/パイロットコーポレーション/ぺんてる 【恒例企画】巳年生まれの書家の年賀状
-

墨2024年9・10月号 290号
¥2,700
【雑誌】 判型:A4変型 並製 頁数:208頁 かな条幅を学ぼう 平安時代に完成し、巻子や冊子などに 小さな文字で書かれてきた「かな」。 その後、展覧会の興隆とともに壁面に映える表現として 昭和三十年前後に生まれたのが「大字かな」です。 細字から大字への展開で、 細字では気付けなかった自分の弱点が見えてきたり、 構成や運筆の難しさに気付いたり。 大字かなならではの魅力をはじめ、用筆や展開方法、 大字ならではの表現のポイントなどをご紹介。 現代書家による鑑賞もお楽しみください。 ★★レッスン 古筆から展開する かな条幅作品の制作 講師/中室舟水 ★コラム 大字かなの誕生と変遷 高橋利郎 ★対談 実作者が語り合う 大字かなの今昔、そして明日 倉橋奇艸×齊藤紫香 鑑賞 現代書家大字かな作品選 ★池野直美 井田智佐子 奥 宣憲 川合広太郎 河合鷹山 金野美和子 杉山玉秀 瀨川賢一 鷹野理芳 谷 蒼涯 谷口成孝 野瀬真理 原田弘琴 福井淳哉 湯川三壽 湯澤 聰
-

『墨』年間購読 (1年間/6冊)
¥17,820
☆17,820円(税込・国内送料サービス) ☆『墨』年間購読【年6冊・奇数月1日発行】 ☆購読期間必須 ⇒ 年 月号から 年間 ※画像は293-298号の例です
-

墨2024年7・8月号 289号
¥2,700
【雑誌】 判型:A4変型 並製 頁数:192頁 もっと知りたい 書道具のあれこれ 道具の良し悪しは 作品づくりに大きく影響を与えます。 のぞむ表現を叶えるために、 使いやすい道具を見つけたいもの。 筆墨硯紙の職人の伝統技のほか、 筆墨店が教える使いやすい道具の選び方、 書家による道具の使いこなし方など、 それぞれの視点で書道具について考えます。 道具の特徴や強みを知り、 選ぶポイントをマスターしましょう。 ★座談会 筆墨硯紙の職人が語る 文房四宝を取巻く日本の現状 畑 幸壯/長野 睦/日枝陽一/片岡あかり ★鑑賞1 現代書家作品選 竹田晃堂/山中翠谷/吉澤鐵之/渡邉 麗 ★産地ルポ1 土佐和紙 尾崎製紙所 基礎知識 道具選びの前に知っておきたい文房四宝 基礎の基礎 産地ルポ2 川尻筆 文進堂 畑製筆所 鑑賞2 墨の美 先人の書 手島右卿/松井如流/深山龍洞 ★コラム1 唐筆随想 談/松村博峰 通信 紙で広げる表現の幅 〜銀座和紙プロジェクトより 文/日野楠雄 ★研究レポート 使いやすい硯とは 文/汪 洋 コラム2 台湾の書道具事情 談/蔡孟宸 連載 ・館蔵の名品 きび美ミュージアム 良寛 草書七言十句 解説/魚住和晃 ・臨書講座 かな 友則集(西本願寺本三十六人家) 指導/佐伯方舟 ・水暈墨章—深淵なる世界— 榊 莫山 ・古典臨書講座 漢字 空海「灌頂歴名」 指導/山中翠谷 ・天真を養う 文/玄侑宗久 ・墨アーカイヴ 村上三島 ・時評 揮灑 文/亀井一攻 ※「中国当代書家二十人」は休載とさせていただきます。 トピックス レポート ★・星弘道・蘇士樹 日中トップ二人展 文/郭同慶 読者参加企画 ・半紙作品募集 審査/佐伯方舟・山中翠谷 ・288号作品募集結果発表 審査/山中翠谷・佐伯方舟 展覧会 [プレビュー] ・石川九楊大全【状況篇】言葉は雨のように降りそそいだ [話題の展覧会] ・叶 春華書画展 ・春季展 新展示棟完成記念 澄懐堂美術館名品展 ・加藤子華書展 ・第 77 回 全国書道展 ・遠藤彊篆刻展 篆刻東西交流展 ・第 78 回 日本書芸院展 ・髙木聖雨書展 ・大楽華雪遺墨展 ・田中徹夫書作展 [話題の書道展より] ・第 73 回 日本書道院展 ・第 46 回 青潮書道会全国展 ・第 84 回 千草会書展 ・第 54 回 臨池会書展 ・第 44 回 翠心選抜展 ・第 48 回 一楽書芸院展 ・第 48 回 書道 笹波会展 ・第 53 回 日書学同人展 墨らんだむ ・書道通信 ・展覧会ルポ ・展覧会アラカルト ・7・8月の展覧会スケジュール ・読者の広場 ・愛読者プレゼント ・新刊ぴっくあっぷ ・バックナンバー一覧 ・常設書店リスト ・次号予告・編集後記
-

墨2024年5・6月号 288号
¥2,700
特集 篆刻のいろは 篆書を印材に刻す営み「篆刻」。 書を学んでいたとしても、印を刻むとなると なかなか難易度が高く感じられます。 しかし、自分の書に自刻印で押印できたら 嬉しさもひとしおのはず。 今特集は現役作家の技術を動画も交えて わかりやすくお伝えします。 また、現役作家の篆刻印を通じて、 篆刻のいろはが学べる 初心者におすすめの企画です。 たまには毛筆を鉄筆に持ち替えて、 自分だけの印を仕上げてみませんか。 名品鑑賞 中国篆刻の名品八選 解説/川内佑毅 学習 篆刻の歴史 中国編/日本編 解説/川内佑毅 視点 近現代日本篆刻における革新 解説/川内佑毅 コラム 悠悠自在に刻る 瀬川敦子篆刻の世界 鑑賞 現代作家による刻リ下ろし企画 井谷五雲/関 青飛/田邊栖鳳/柳澤玉暎/和中簡堂 SNS連動企画 第3弾 あなたの自刻印見せてください! ★レッスン 10工程で楽しく学ぶ 篆刻入門講座 —道具選びから側款の刻し方まで— 講師/松尾碩甫 ★インタビュー 獨行道 原田歴鄭 ★知識 二世中村蘭臺の篆刻 文/松尾碩甫 対談 日本と台湾、篆刻や書の違いを“深刻る” 蔡 孟晨×松尾碩甫
-

墨2024年3・4月号 287号
¥2,700
特集 心を打つ書 なぜか心を揺さぶられる書があります。 なぜか目をそらすことのできない書があります。 迫力のある「動」の書だけでなく、 静謐で落ち着いた「静」の書にも 人を惹き付ける魅力があるものがあります。 書法や技巧にとらわれず、 まっすぐに語りかけてくる作品の魅力と その奥にある何かを探ります。 鑑賞 遺偈と墨蹟 選/萱のり子 ★知識 成田山書道美術館 学芸員選 心を打たれた館蔵品 クローズアップ なぜ心打つのか 三輪田米山の書 ★対談 尾西正成×髙橋利郎 何が心を惹きつけるのか 視点 書家の視点で味わう墨蹟 選・文/尾西正成 インタビュー 個性の凸凹を削らずに磨いて輝かせる 西里俊文 ★レポート この道より我を生かす道なしこの道を歩く 企画展「書が映す武者小路実篤」
-

墨2024年1・2月号 286号
¥2,700
特集 かなのチョイスと表現 日本独自の美しい文字として発展してきたひらがな。 そして、かな書道を学ぶうえで 避けては通れない変体仮名の学習。 学校で習ったひらがなであっても、 作品に仕上げるのは難しいのに、 さらに覚えなくてはならないのは大変です。 本特集ではかなの作品を通じて、 日本特有の文字「かな」の表現を考えます。 今一度、変体仮名の使い分けや そこから生まれる効果の違いを考えてみませんか。 ★鑑賞 変体がなの表現からみる香邨作品 選・解説/原 奈緒美 ★鑑賞 現代書家による書き下ろし作品 石澤桐雨・土岐姸子・馬場紀行・渡邉之響 ★レッスン かなと「変体がな」を使い分けよう 講師/原 奈緒美 コラム SNSで発信! かな書道の魅力と変体がなのおもしろさ ★鑑賞・学習 古筆で学ぶ変体仮名 選・解説/中室舟水 ★対談 かな作品 制作の裏側―変体仮名の可能性― 岩井秀樹×財前 謙 コラム スマホで古文書を読もう! くずし字解読アプリ「古文書カメラ®」
-

墨2023年11・12月号 285号
¥2,700
今年も終盤。 去る一年を振り返り、来る一年に祈りを込めて、 手紙で思いを伝えたい。そんな季節でもあります。 手紙を書くということは、 自分の気持ちを文字にすると同時に、 受け取った相手の気持ちにも寄り添う、 そんな行為なのだと思います。 敬意、お礼やお祝いの気持ち、 お願い事や叱咤激励、ユーモア。 折々の手紙には、 そんな気持ちとともにその人の素顔や 以外な一面が垣間見られます。 本特集では、手紙が運ぶ思いと そこから生まれる コミュニケーションをご紹介。 「卒意の書」ともいわれる 手紙をめぐる世界へとご案内します。 歴史上の手紙たち 文/住川英明★ 「てがみ」って何? 文/岩下哲典 幕末の日本人と手紙 文/岩下哲典 近代画家たちの手蹟 文/住川英明 コラム 手紙の効用 文/井原奈津子★ 手紙は気持ちのキャッチボール★ 小堀遠州の酒井忠勝宛書状 森岡 隆
-

墨2023年9・10月号 284号
¥2,700
特集 スッキリ解決! 書の疑問 書道をつづけるうちに自然と生まれる素朴な疑問。 臨書や書作、道具のこと、 さらに師匠や教室、展覧会のこと……など 今さら聞けないけれど知りたいことに、 Q&A方式で、各分野の専門家たちがズバリ! ていねいにお答えします。 書へのさまざまな疑問をスッキリ解決しましょう。
-

墨2023年7・8月号 283号
¥2,700
【特集 わたしの好きな名句・名文】 最近、心動いた言葉はありますか? 自分の心を代弁してくれるような 名句・名文との出合いが、創作への扉を開いてくれます。 和歌や短歌、漢詩、文学作品などから 好きな言葉を選び、自分らしく表現しませんか。 現代若手作家41名による作品を通して 名句・名文の書への展開を紹介します。 選んだ名句・名文を書く ・かな編 奥江晴紀 川合広太郎 坂井孝次 棧敷東煌 瀨川賢一 谷口成孝 西田 健 野瀬真理 野村 崇 原田弘琴 渡邉之響 渡辺貴彦 ・漢字編 新井龍雲 池谷天外 石川青邱 大田鵬雨 尾西正成 鹿倉碩齋 草津祐介 阪野 鑑 佐川峰章 櫻本太志 佐藤義之 角田大壤 西村大輔 長谷川香濤 深田邦明 細川太翠 松岡碧惺 水川芳竹 吉澤衡石 吉澤太雅 ・水墨画編 伊藤 昌 新恵美佐子 ・漢字かな交じり書編 大八木耕一 金子大蔵 種家杉晃 千代倉桜崖 ・篆刻編 権田逸廬 辻 敬齋 山本山罍 コラム 先人の名句・名言 日本書論編 中国書論編 近代文人編 現代書の巨匠編
-

墨2023年5・6月号 282号
¥2,700
【特集 書と暮らし】 今を生きる自分の心を表すぴったりの言葉は? 心躍るうたの一節は? 思いを言葉にのせて小さな作品で表現しませんか? 公募展出品に縛られない自由な書表現をご提案。 気軽に触れて、暮らしに寄り添う小品は心を豊かにします。 部屋に合うお洒落な表装もご紹介 ・エッセイ 書のある暮らし 文/名児耶 明 ・クローズアップ 遊びごころが「書」をきわめる 村上翠亭 ・ピックアップ 身近に飾りたい色紙いろいろ ・レッスン 生活を彩る小品 色紙に万葉集を書く 講師/大石三世子 ・インフォメーション 泊まってみたい! 「書」のあるホテル 等々
-

墨2023年3・4月号 281号
¥2,700
特集 臨書 再発見 書の学びのはじめであり終わりでもある「臨書」。 古の書人から贈られた多くの古碑・法帖は、 私たちに技としての筆路ばかりでなく筆意、 そして書の美を教えてくれます。 名を成した書の大家も、終始、古典作品と向き合い、 臨書で得たものを創作に投影してきました。 ここでは、先人たちの臨書哲学や名臨書を通じて、 文字の形を写す作業とは違った臨書の楽しさ、 魅力を再発見してみましょう。
-

墨2023年1・2月号280号
¥2,700
【特集 王羲之と蘭亭序】 書学者の永遠のバイブル──王羲之「蘭亭序」。 永和九年(353)3月3日、 会稽山陰(浙江省紹興市)の蘭亭にて 王羲之が開いた雅会で詠まれた詩集の序文の草稿です。 真跡が失われた後も、複製を通して多くの書人が臨書を試みてきました。 名筆であるだけでなく、名文でもあったからこそ 生まれた世界観や文化も見逃せません。“書聖”王羲之の人物像をはじめ、 「蘭亭序」が時代を超えて愛され続ける所以とその魅力に迫ります。
-

墨2022年11・12月号279号
¥2,700
【特集 心ととのえる書】 世の中のさまざまな不安や悩みが晴れないうちに 今年も終わりが近づいてきました。 次の一年こそは心穏やかにありたい……。 そんな願いは決して現代の私達だけのものではありません。 古来、人々は神仏に願う気持ちを文字にすることで心を整え、 またそうした書を見ることで心調えられてきました。 奉納された書や写経を中心に、あらためて 心をこめて書かれた文字の力に触れてみたいと思います。 ・グラフ 平家納経/かな心経 ・エッセイ そこに自由はあるんか? 文/玄侑宗久 ・読解 意味を知ろう 唱えてみよう 般若心経 ・鑑賞 般若心経を味わう ・実習 心をととのえて 美しく書いてみよう 十句観音経 ・ミニ鑑賞 心ととのう仏教の名言 荒木大樹 ・ピックアップ 御朱印集めを楽しもう ・レポート 東大寺 昭和大納経 ・エピローグ 「今年の漢字」で振り返る
-

墨2022年9・10月号278号
¥2,700
美術展ナビで紹介されました! 【BOOKS】書を楽しみたい人のための雑誌『墨』9・10月号は「書に出会える美術館」 【特集 今こそ行きたい! 書に出会える美術館】 芸術として、あるいは書道の学びの資料として、 日本各地の美術館・博物館・記念館に展示される書作品。 名作あり、隠れた逸品あり。そして収蔵品への敬慕が溢れた展示。 静かな館の佇まいの中、作品と対峙するひとときは その土地その館を訪ねてこそ味わえるものです。 情況が許すなら少し出かけてみませんか。本物の書に会いに。 ・ 美術館・博物館の基礎知識 ・掲載美術館インデックス/本特集をご利用の前に ・周囲の公園もまるごと書の迷宮 成田山書道美術館 ・日本のザ・ミュージアム 東京国立博物館 ・特別デジタル展 故宮の世界 ・学芸員の奮闘! 台東区立書道博物館/中村不折記念館(併設) ・小野道風誕生伝説の地に 春日井市道風記念館 ・エッセイ 誰もいない美術館を楽しむ 文/武田 厚 ・地元で身近に名品を 徳島県立文学書道館 ・ミュージアムグッズ探見! 文/大澤夏美 ・かわら版 再開が待たれる美術館 ・書に出会える美術館カタログ 国立博物館 書道専門の美術館 個人書家記念館 旅してみたい美術館 個人コレクション美術館
-

墨2022年7・8月号 277号
¥2,700
【特集 漢詩は難しくない!?】 作品の題材として欠かすことのできない漢詩。 「そもそも漢詩って何?」「むずかしそうで苦手……」 そんな声にお応えして、基礎知識、作品を詠む・書く・味わうためのテクニック、先人の名筆などをご紹介。 漢詩がわかれば、作品表現が楽しくなります。 いま、あらためて漢詩に入門してみましょう。 ・漢詩の基礎知識 監修/石川忠久 文/香川 亨 ・鼎談 漢詩の楽しみ方 石川忠久・菅原有恒・吉澤鐵之 ・実習 パズル感覚で漢詩を作ってみよう 指導/吉澤鐵之 ・鑑賞1 筆致と詩で愉しむ中国の名筆 作品選定・解説/尾川明穂 釈文・読み下し/長谷川 智 〈現代日本編〉漢詩表現の粋 選/編集部 ・視点 日本漢文クレオール類型論 文/松宮貴之 ・コラム 漢詩の音 監修/荘 魯迅 ・制作 好きな漢詩で作品を書こう 講師/宮負丁香 ・必須 漢和辞典を引こう 監修/吉澤鐵之 ・鑑賞2 詠むことと書くこと 文/谷村雋堂 ・コラム 「からのうた」のつくりかた 文/横山悠太 ・レポート 漢詩は作れる! 実践授業より 文/佐藤海山
-

墨2022年5・6月号276号
¥2,462
【特集】 書道具のいま 道具を選び使う楽しみは、書の醍醐味のひとつ。 同時に、道具についての多くの迷いや疑問にも出会います。 本特集では、書家や筆墨店、メーカーなど、書道具をよく知る人にそれぞれの立場からのご意見やアドバイスをいただきました。 商品紹介のページはありません。 書道具を取り巻く事情を知ることで、これらを選び使う楽しみと書の世界のおもしろさが 新たに感じられることでしょう。 ・奈良に息づく墨作り 古梅園/喜壽園/墨運堂 ・書と筆 道具に秘められた力 筆の歴史 文/村田隆志 筆からみる名筆 監修/村田隆志 ・先人の道具たち 日比野五鳳 青山杉雨 榎倉香邨 ・道具を味方に 筆墨店へ行こう 書家・松尾 治/上尾松島堂 ・レポート1 どこへ向かう? 液体墨のいま、未来 開明/呉竹/墨運堂 ・レポート2 現代の筆づくり 筆庵 ・レポート3 大学の教育現場から 書道具・文房四宝 文/日野楠雄 ・レポート4 老舗紙商と和紙のいま 小津和紙 ・レポート5 筆墨店&工房のウェブ展開 ・レポート6 中国産書道具の現状とは ・レポート7 筆墨店の来し方 行く末 賛交社 ・実録! 書道具ひと揃いへの道 ならや本舗 ・資料室1 全国 書道具を知るための資料館&体験スポット ・資料室2 全国 筆墨硯紙店リスト